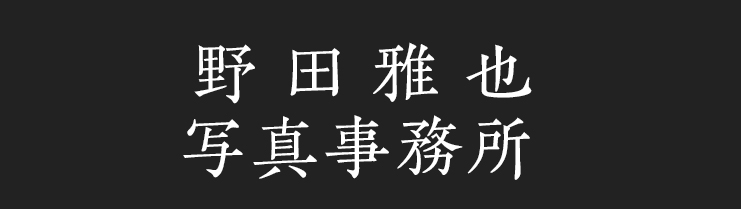「朝日新聞 AERA (アエラ)」(2012年3月掲載)
津波で壊滅した岩手県大槌町。ひょうたん島のある赤浜地区の岸辺に、震災後に最も早く事業を再開した岩手造船所がある。陸に打ち上げられた漁船や小舟が修理のために運び込まれ、被災地に機械音を響かせる。
高さ6.4メートルの防波堤より海側にある造船所は、係留していたサンマ船など13雙とともに、真っ先に流された。被災した船には、定期検査のため地震のわずか2時間前に修繕用ドックに上げられた観光船「はまゆり」があった。「屋根の上の遊覧船」と脚光を浴びた釜石市のあの船だ。
赤浜小学校の裏山に避難した川端義男社長(70)は、「第2波の引き波で、民宿『あかぶ』さんの屋根にポンと乗りあげた」とその始終を見た。人様の屋根で絶妙にバランスを保つ観光船に「申し訳ないやら、恥ずかしいやら」。北海道の根室港に流れ着いた船もあった。
私が赤浜地区を二度目に訪れた4月6日、折れ曲がった鉄骨や木材を掻きわけ、道具を拾い集める男性を見かけた。その人が川端さんだった。当時、惨状を前に再建をあきらめていたが、「造船所が動かなければ、漁師も立ち上がれない」と自らでがれき撤去を始めた。幸いにも、船を引き上げるためのレールが残っている。「もう一度できる」と確信した。被災地では、まだ遺体捜索が続けられていた頃だ。

明治時代から続く造船所を4代目として継いだ川端さんは、昭和20年の大槌空襲の後、焼け野原から再建する父の姿を見て育った。「無ければ、造ればいい」という言葉通り、流れ着いた廃材で作業小屋を建て、海水に浸かった機器類を整備した。従業員1名が犠牲になったが、生き残った14名の仲間も避難所から通い、手伝いを始めた。長年の経験をもつ熟練工たちは手先の感覚で鉄パイプを曲げ、海水で錆びた鉄板をガスバーナーで切り抜く。図面もないが、船のディーゼルエンジンを利用した船舶巻き上げ機を手作りした。これで70tまでの小型船をドックに引き上げることができる。エンジンが黒煙をあげ、造船所は復活した。
81歳の船大工、東満衛門さんは寝たきりだった妻を津波で亡くした。倒壊した自宅のベッドのそばに横たわる姿を見つけた。人生を共に歩んできた妻への想いを胸に、ふたたび造船所へ戻った。「仕事をしながら、パタッと逝けば本望」。漁に使用するタモの柄を、杉の丸太から鉋ひとつで削り造る。造船所の仲間からは、「あの人しかできない凄腕だ」と仰ぎ見られる。
小舟の補修作業を行う石村行輝さん(60)は、「船底しかなかった」とがれきの中で発見されたアワビ漁の磯舟を指差した。持ち主の行方は今もからない。漁を継いだ息子から、「親父の形見に修復してほしい」と頼まれた。石村さんは「どの舟にも想いが込められている」と丹念にヤスリをかける。

本格的に造船所が始動すると、馴染みの機械工やペンキ屋などが、「仕事があれば声かをけて下さい」と訪ねてきた。川端さんは「誰もが立ち上がろうと必死だ。協力し合ってみんなが飯を食えればいい」と助け、助けられる関係を大切にする。ある漁師は、「魚が捕れたら、少しずつ払うから」と修理を終えた船に大漁旗を掲げて沖に出た。仕事は稼ぐためではなく、人と人とを繋ぐためにある。
年が明けた1月5日、大槌町では震災後に初めてとなるサケの定置網漁が再開された。港を出航した2隻の久美愛丸は、岩手造船所で修理されたもの。サケを甲板に引き揚げるタモ網は、東さんが作り上げたものだ。初漁の翌日、男たちの弁当には焼き鮭が添えられ、白米には新鮮なイクラがたっぷりとのっていた。海の幸の輝きに、私は営みのつながりを感じた。
確かな一歩を踏み出したが、湾に船が行き交う日は、遠い。